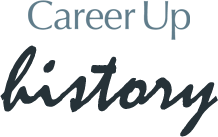~第7章~
政策的な変遷
国際的なスポーツとジェンダーに関する変遷
国内のスポーツとジェンダーに関する変遷
スポーツにおいてジェンダーの平等政策の中で語られるようになったのは、アメリカで制定された、教育改正法第9編(以下、「タイトル IX」とする)が初めてである。タイトル IXは1960年頃アメリカで拡大したウーマン・リブの女性解放運動の後押しを受け、連邦政府から補助金を受けている全ての学校において、男女の違いによる差別を認めないことを法律で定め、部活動のようなスポーツプログラムにも適用されることとなった。タイトルIXの影響は大きく、高校生の部活動参加率が大幅に増加し、大学進学のためのアスリート奨学金が女子学生にも平等に分配されることが保証されたことで、女性の高等教育の進学を後押しした。大学は男女のチーム数を同等にすることが求められ、大学女子チームが増加し、女性指導者の雇用も拡大した。
1975年には、欧州評議会が「ヨーロッパスポーツ・フォー・オール憲章」を策定し、スポーツを享受することがあらゆる人の人権となった。1978年には、国際連合教育科学文化機関(以下、「UNESCO」とする)が「体育・スポーツ国際憲章」を制定し、翌年の1979年に開催された第34回国連総会にて、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下、「女子差別撤廃条約」とする)」が策定された。同条約の第3部第10条に「スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機会」が記載され、国連が発表する女性に特化した政策文書の中で初めてスポーツに関する事柄が記載された。
その後、女性とスポーツの政策的な変化が活発になったのは、1994年にイギリスのブライトンで開催された「ブライトン会議」以降である。同会議の中で、女性とスポーツを推進するための10の原理原則となる「ブライトン宣言」が採択され、包括的に女性とスポーツを推進するための国際女性スポーツワーキンググループ(以下、「IWG」とする)が設立された。IWGや、同じくブライトン会議をきっかけに設立したWomen Sport International(以下、「WSI」とする)の活動がブライトン会議以降、国連や国際オリンピック委員会(以下、「IOC」とする)の女性とスポーツに関する取り組みに影響を与えた。1995年の第4回世界女性会議にて採択された「北京宣言」と「北京行動綱領」では、スポーツと身体活動に関して触れられ、IOCは同年にブライトン宣言に署名をし、女性スポーツワーキンググループを立ち上げた。
IWGは1994年以降、4年に1度「IWG世界女性スポーツ会議」を開催し、政策提言文書を発表している。IOCは1996年に「第1回IOC世界女性スポーツ会議」をスイスのジュネーブで開催し、女性の役員の割合を少なくとも10%以上にすることを掲げ、各国際競技連盟に女性スポーツ委員会を設置することを推奨した。また、オリンピック憲章に初めて「女性」の文字が追記されたのも、同会議の成果である。その後、2012年のロサンゼルス大会まで4年に1度「IOC世界女性スポーツ会議」は継続し、2012年会議において採択された、「ロサンゼルス宣言」により、今後UN Womenとの連携強化を図る方針が示された。そのため、同年8月にはIOCとUN Womenが覚書協力を締結し、協力関係は現在まで継続している。
2014年4月にIOCはアジェンダ2020を発表し、提言11に「男女平等を推進する」が明記された。この中には、女性の参加率を50%にすること、そして男女混合種目の増加が具体的な取組として含まれた。2017年にはIOCの中でアジェンダ2020の提言11をさらに具体的にするための、Gender Equality Review Projectのワーキンググループが発足し、2018年3月の第62回国連女性の地位委員会において、「Gender Equality Review Project25個の改革案」が正式に発表された。また、2018年はIOCの女性役員の割合が過去最高の42.7%となった年である。
国内のスポーツとジェンダーに関する変遷
国内における戦後の女性スポーツの変遷は、1954年の日本女子体育連盟の設立から遡る。ダンス教育という切り口から女子体育の普及と指導者育成に長年貢献してきた。その後、1981年にはアメリカの女性スポーツ財団(以下、「WSF」とする)の日本支部であるWSFジャパンが立ち上がり、1992年にJOC初の女性理事の誕生に貢献した。1980年代~90年代は国内の女性参画に関する政策が大きく動いた期間である。日本政府が1985年に国連の女子差別撤廃条約に批准をし、1986年には雇用機会均等法が施行、1994年には総理府が男女共同参画室及び男女共同参画審議会を設立した。また1999年には男女共同参画社会基本法が施行し、男女共同参画社会に政策的な追い風となった。
その頃、IWGの流れを汲んで、1998年にNPO法人ジュースが設立し、2006年に熊本県で「第4回IWG世界女性スポーツ会議」が開催されるまでの間、加速度的に日本の女性とスポーツは変化した。2000年に発表された、男女共同参画基本計画の中においても、スポーツに関する文章が組み込まれた。これは、国内の政策文書の中で初めてスポーツと女性に関する事項が記載された文書となった。2001年にJOCは、IWGが推進する「ブライトン宣言」に国内の統括団体として初めて署名をし、翌年の2002年には女性スポーツプロジェクトがJOC内で発足した。同プロジェクトは2003年に女性スポーツ専門部会へと発展することとなった。
スポーツ関連の政策文書の中で初めて「女性」について言及されたのは、2006年に改訂された「スポーツ振興基本計画」である。女性がスポーツに参加しやすい環境づくりなどが明文化された。2011年からようやく「女性とスポーツ」に特化した取組に国家予算が投入されるようになり、2013年の3月に策定された「スポーツ基本計画」に、女性アスリートへのサポートが言及され、現在まで続く、「女性アスリート育成・支援」事業が開始された。同プロジェクトが功を奏し、2016年のリオオリンピック競技大会を除いては、女性のメダル獲得率は男性よりも高いものとなった。
2017年には、IWGの「ブライトン・プラス・ヘルシンキ2014宣言」(2014年に「ブライトン宣言」から改訂)に日本のスポーツを統括する全ての団体(スポーツ庁、日本スポーツ振興センター、日本オリンピック委員会、日本障がい者スポーツ協会/日本パラリンピック委員会、日本スポーツ協会)が合同で署名をし、「女性とスポーツ」に関する取組を推進することを国内外に表明した。2018年の男女共同参画白書では、前代未聞の約50ページにわたり、スポーツ界で女性が直面するあらゆる課題と日本政府の施策について特集が組まれた。JOCは2018年度にスポーツ庁女性スポーツ推進事業「スポーツ団体における女性役員の育成事業」を受託し、スポーツ界における女性理事の支援及び育成に力を入れている。少しずつではあるが政策レベルにおける女性のサポートは拡大しているものの、女性労働者の法的保護を評価している2019年度版「女性・ビジネス・法律2019」(世界銀行)において、日本は187か国中83位とG7の国々の中では最下位であった。また、世界経済フォーラムが毎年発表している「ジェンダー・ギャップ指数」においても、2019年は153カ国中121位と2018年のレポートから11位順位を落とした。その要因は女性の政治参加度の低さである。国内の競技団体における女性理事の割合は、2019年12月のJOCの発表によると、未だ16%に留まっている。
2020年に向けて高まるジェンダーの多様性に関する取組
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下、東京2020)の招致は国内のジェンダーの多様性に関する政策を後押した。大会のレガシープログラムであるスポーツ・フォー・トゥモロー事業の一環で、スポーツ庁は国際スポーツ人材育成拠点の構築事業を進めており、2015年より同事業を受託している筑波大学が修士プログラムの「つくば国際スポーツアカデミー(TIAS)」を実施している。同カリキュラムの中では、専門的にスポーツとジェンダーについて学ぶジェンダーモジュールが組み込まれた画期的なカリキュラムとなった。東京2020開催の後押しによる、ジェンダーに関する政策的取組は女性だけに留まらない。オリンピック憲章が定めるオリンピズムの根本原則によると、性別や性的指向の違いによるいかなる差別を受けないと定められている。
2014年のソチオリンピック開催直前にロシア政府が制定した「同性愛宣伝禁止法」を受け、IOCが翌年の2015年にオリンピック憲章を改訂し、「性的指向」による差別を禁止することを根本原則に追記した。オリンピック憲章の遵守のために、東京2020組織委員会が2016年1月に制定した「持続可能性に配慮した調達コード基本原則」の中で、サプライヤー及びライセンシーに対し、製造・流通過程において、性別、性的指向等による差別やハラスメントを排除することを記している。また、東京都は2018年10月に「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を策定し、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別の解消並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の推進を図ることを条例で定めた。
スポーツ界におけるジェンダー平等の取組は、これまでドラスティックな変化が生じにくい状況であった。しかしながら、2013年に東京2020の開催が確定して以来、IOCをはじめとする国際社会からの外圧や注目が日本に向けられ、政策面での変化がはっきりと見える形で進められてきた。これからの日本が東京2020に向けて期待されていることは、策定された政策の実行能力であり、現行の政策文書では包括できていない部分を検証していくことが必要である。